未就学児の支援事例
小学生の支援事例
中学生の支援事例
高校生の支援事例

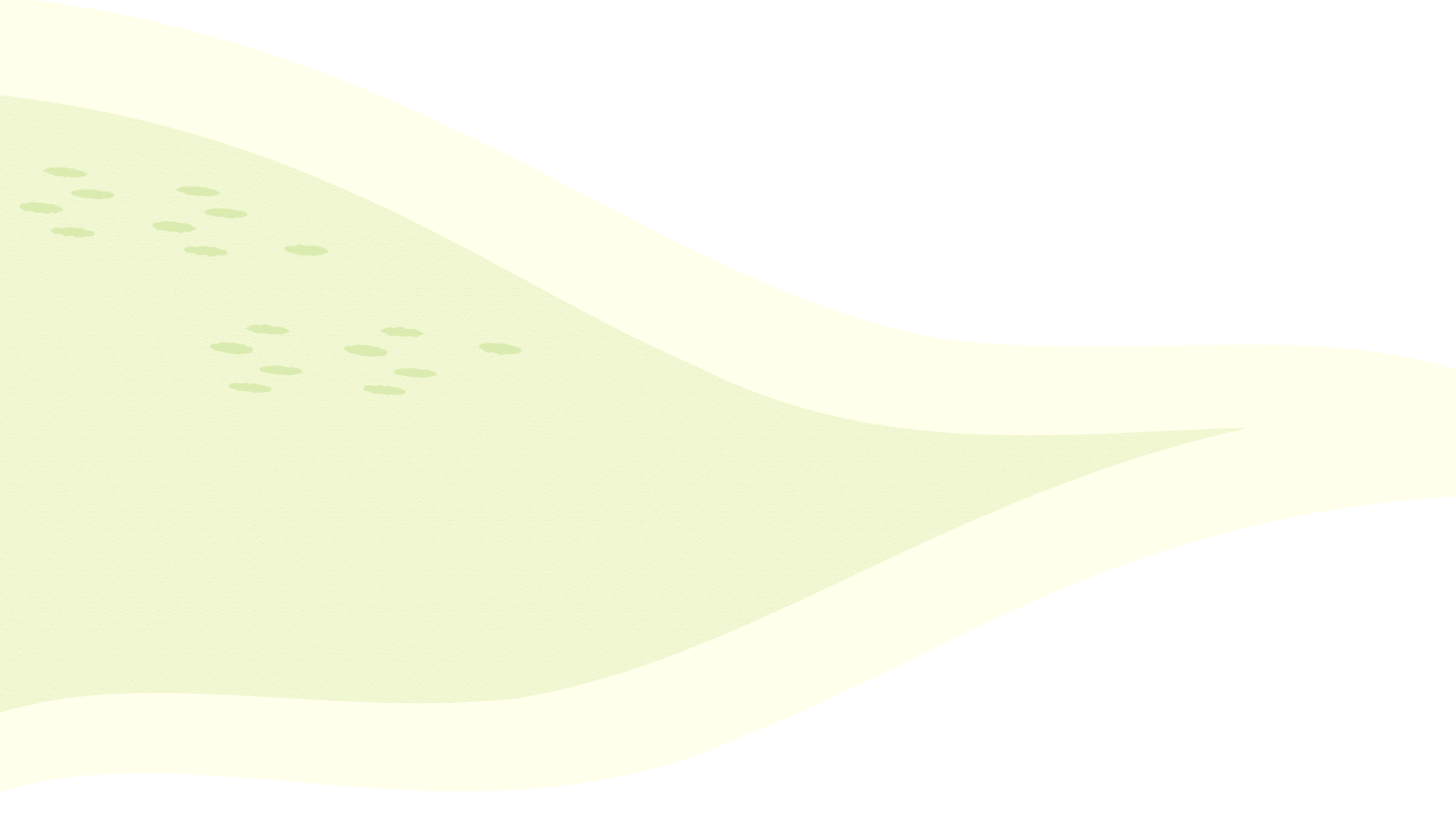
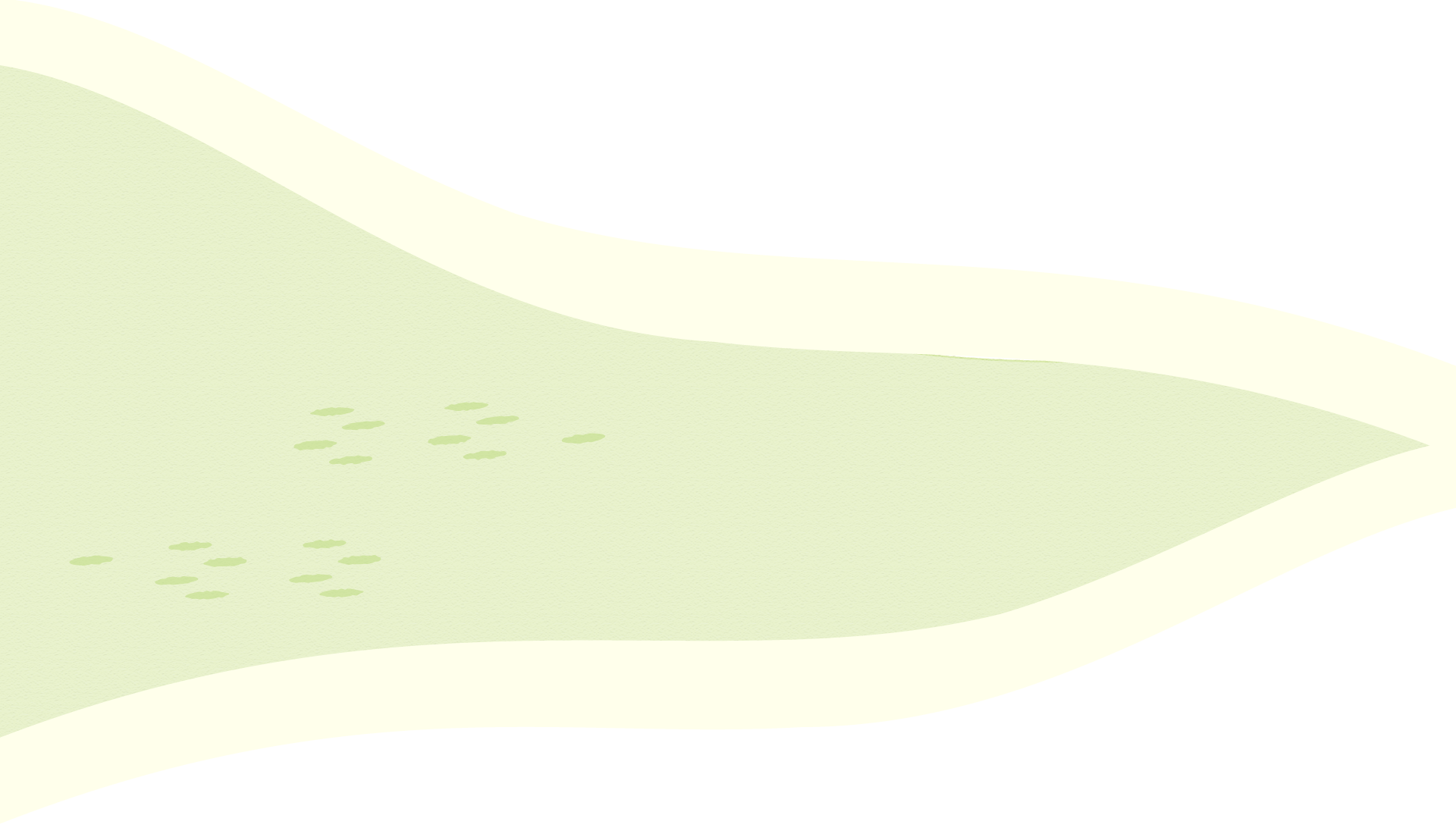

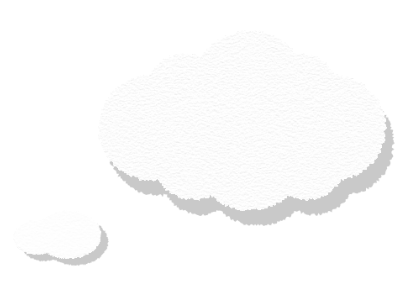
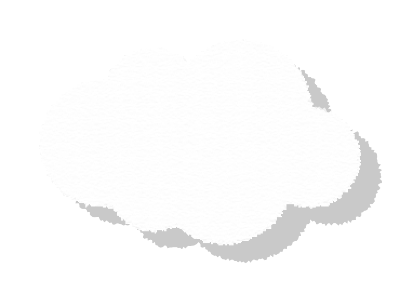
ハッピーテラスでの療育を通して、大きな成長を遂げたお子さまの支援事例です。
療育方針・支援内容とともにご紹介します。

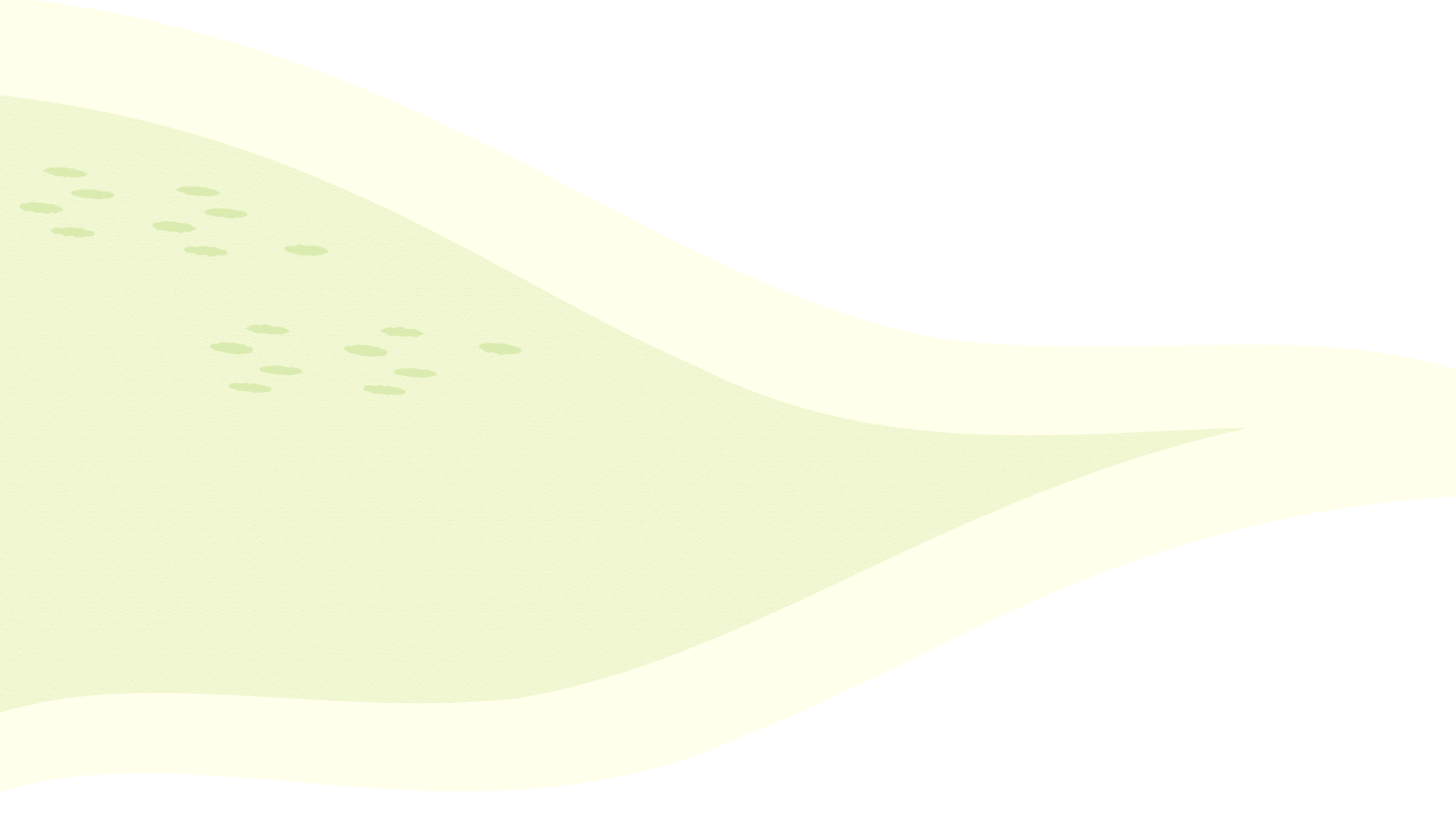
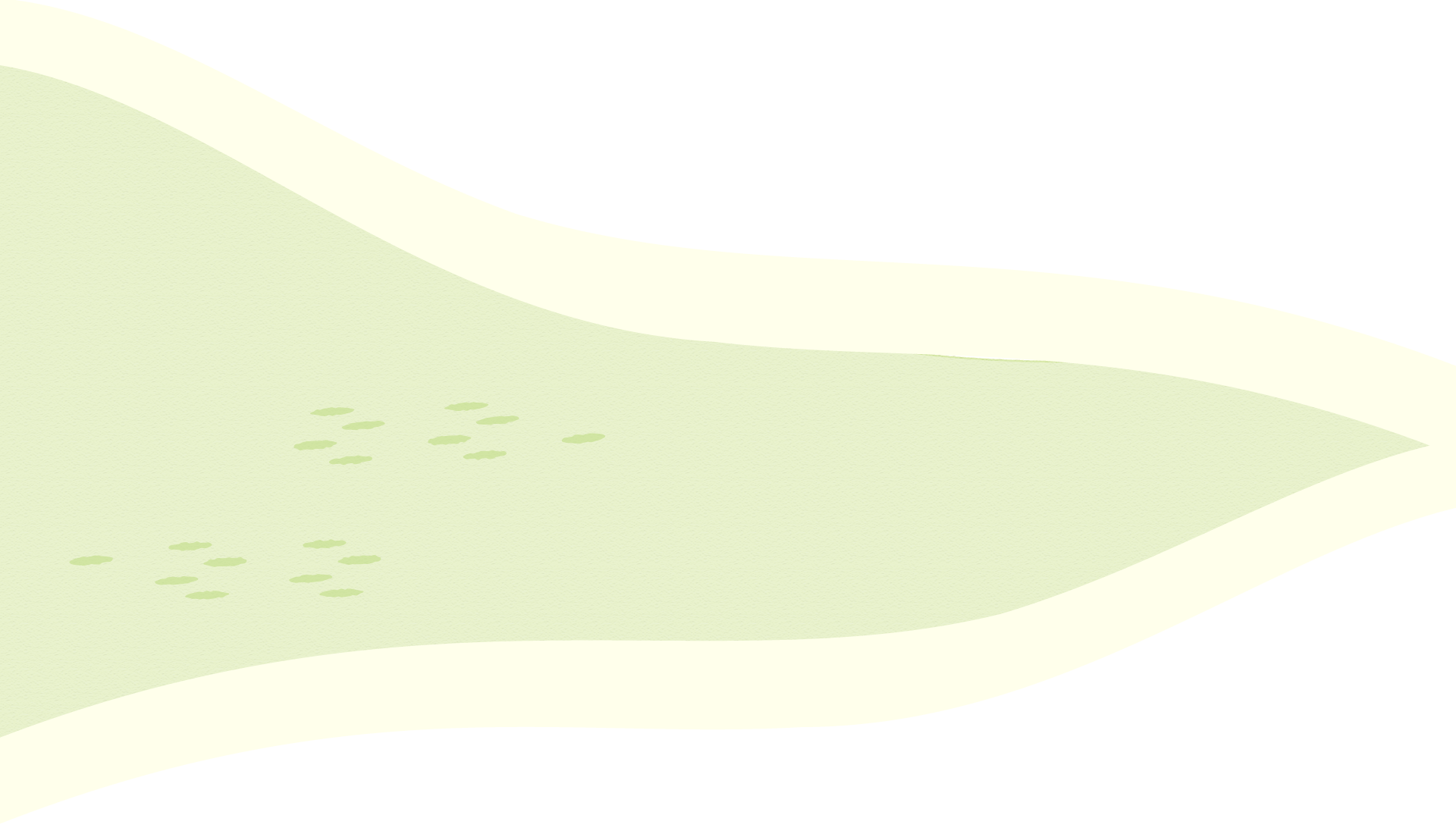


「できる!」を増やすプログラムの無料体験会を開催中。
資料請求のみのご希望も承っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。