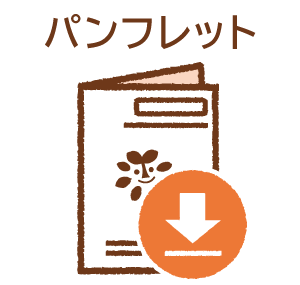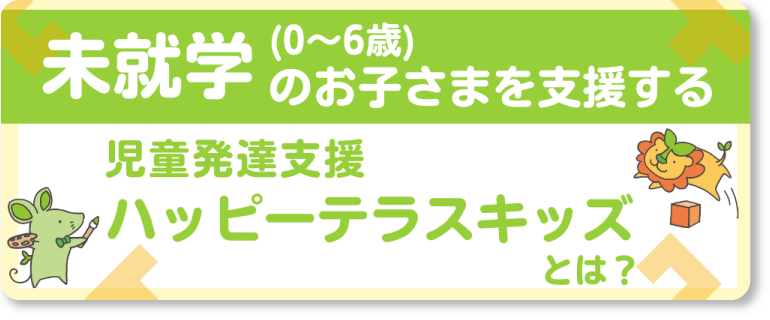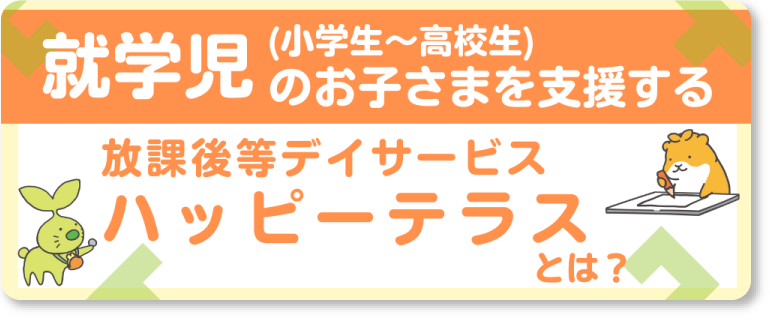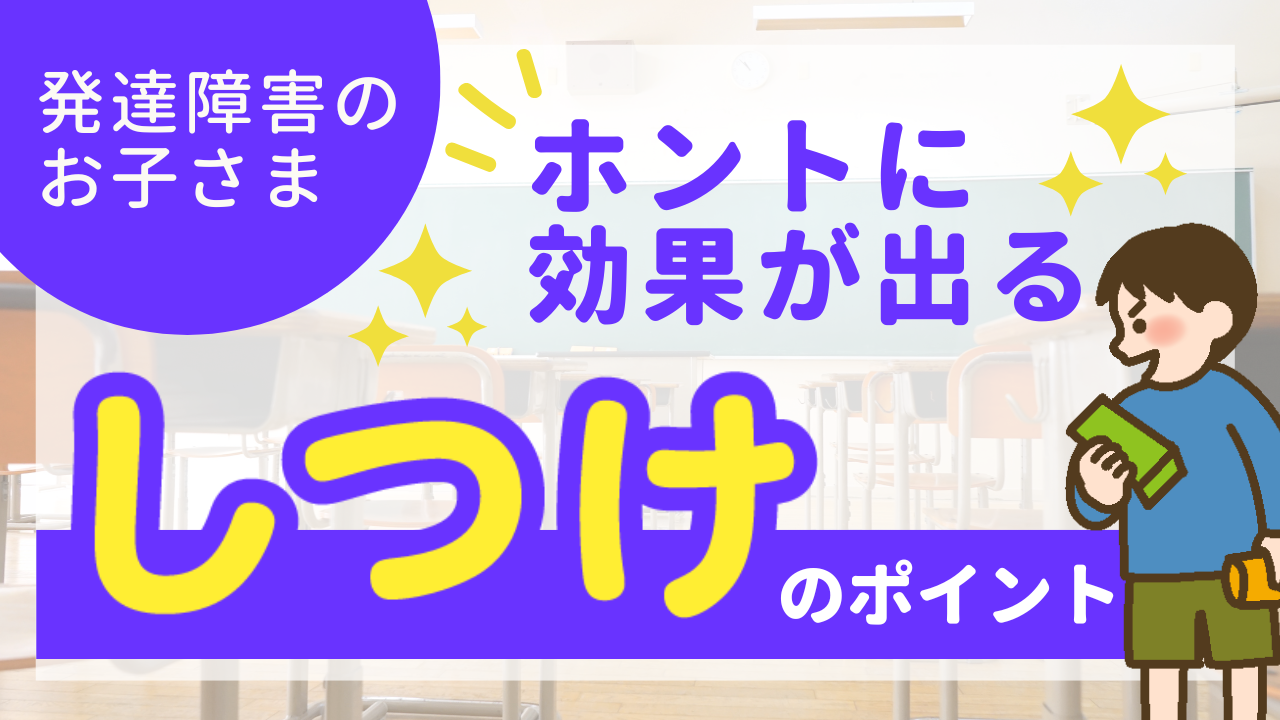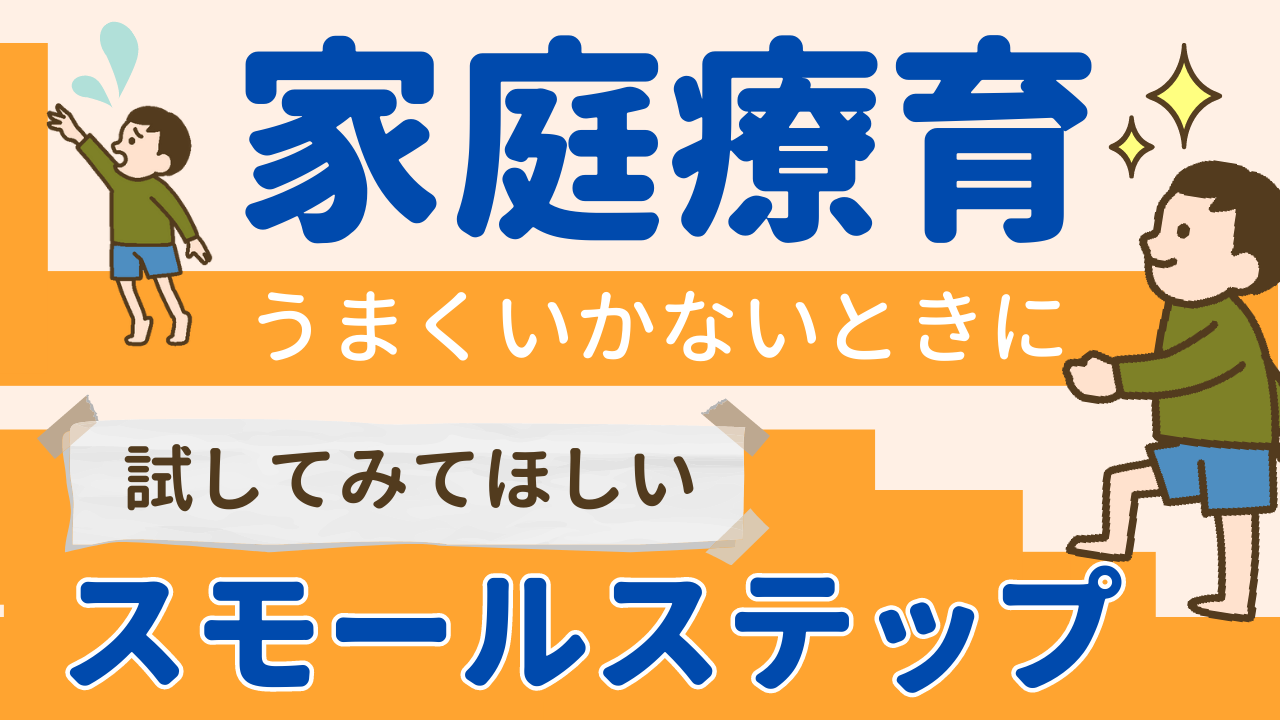発達障害の子どもの「遊び食べ」|原因とサポート方法
![]()
食べ物を手でぐちゃぐちゃにしたり、食器やごはんを投げ落としたり、食事中に席を立って歩き回ったりする「遊び食べ」。
掃除や洗濯が増えたり、せっかく作ったごはんが台無しにされたり、周囲から冷ややかな視線を浴びたりして、「早く終わってほしい。いつ終わるのか」と悩んでいる保護者の方も多いのではないでしょうか。
子どもの発達過程において多く見られることがありますが、発達障害のあるお子さまの場合、遊び食べが長期化することがあります。
今回は、発達障害のあるお子さまの「遊び食べ」の原因とご家庭でのサポートテクニックについて紹介します。

目次
「食事」に関する悩みが多い理由
発達障害があるお子さまの場合、その特性によって「食事」に関する苦手があることがあります。特性が原因である場合には、「わがまま」ではなく「どうしようもない」ことなのです。
そのため、一般的に語られている食事のしつけが通用せず、むしろ特性に配慮をしない指導をすることで、お子さまに大きなストレスや苦痛を与えてしまうことがあります。
お子さまの特性にあわせたアプローチをすることが大切です。

発達障害と遊び食べ
「遊び食べ」とは、ごはんやおやつを食べながら遊びはじめてしまうことを言います。食べ物を握ったりわざと落としたり、スプーンで皿を叩いたり、食事中に別のことをはじめたりするなどです。
主な原因は、子どもの「探索行動」によるものと考えられており、成長過程でみられることがあります。探索活動とは、見るもの・聞こえるものや、知らないものごとに対して強い好奇心をいだき、確かめながら知ろうとする行動をいいます。
ごはんや食器のかたさ・温度・質感などを手で触ることで、その感覚を確かめているのです。
そのほかに、「集中力が続かない」「お腹が空いていない」「保護者の方の注意をひきたい」などが原因となることもあります。
子どもの発達の過程で多くみられるものですが、一般的におおよそ3歳まで続くと言われています。発達障害があるお子さまの場合は、特性により「遊び食べ」が長期的に続くことがあります。
原因として考えられる特性について解説していきます。
ASD特性 感覚特性(感覚過敏・感覚鈍麻)
「感覚過敏」があり、自分の好きな刺激を求める傾向があるお子さまの場合は、特定の「触感(手触り・肌触り)」を好み、食べ物を手や口で触れることが「気持ちいい」と強く感じるケースがあります。好きな感覚を得るために食べ物をこねたり握ったりしてしまうのです。
「感覚鈍麻」があり、空腹を感じづらいお子さまの場合には、「食べたい」という気持ちが沸かず、目の前にあるごはんで遊んだり、食事以外の行動をとってしまったりするケースがあります。
社会的なルール(マナー)の習得が遅れている場合には、「食べ物で遊んではいけない」というルールが理解できず、ごはんを手で触ったりすることが長期化するケースがあります。
ASDがあると常識を習得しづらい?上手な教え方は|中高生向けをあわせてお読みください。
ADHD特性 衝動性・多動性・不注意
「衝動性・多動性・不注意」がある場合、食事中に立ち歩いてしまうケースもあります。
自分の欲求や行動を抑えきれずにごはんを食べているのにゲームをはじめたり、目に入った気になるもののほうに歩いて行ったりすることがあります。
集中力が続かず、「食事」をすることに飽きてしまうこともあります。
特性によって感情浮き沈みが激しい場合には、日によって食べる量が異なる「ムラ食べ」が見られることもあります。
障害の有無を問わず、子どもは集中し続けることのできる時間が短いものです。年齢に応じて、徐々に持続時間が増えてきますが、ADHD特性があるお子さまの場合には、集中の継続が難しいことが多いため、食事中に注意がそれることがしばしば見られます。
その他の原因
 食事をすることが苦手
食事をすることが苦手
発達障害のあるお子さまは、ネガティブな記憶が鮮明に残りやすい傾向があります。食事中に嫌な経験(叱られた、おいしくないものを食べた、やけどをした等)をした場合には、そのときの記憶がフラッシュバックすることがあり、食事をすること自体が「嫌なこと・面倒くさいこと」になり、進んでごはんを食べなくなってしまうケースがあります。
口腔機能(噛む・飲み込むなど)、手先に不器用さがある場合には、食事をするための動作が苦手なこともあります。ASD特性があるお子さまの場合は、「偏食」が食事嫌いの原因になっている可能性も考えられます。発達障害の子どもの「偏食」|原因とサポート方法もあわせてお読みください。
 試し行動
試し行動
わざとごはんや食器を落として、保護者の方の様子をうかがっている場合には「試し行動」である可能性が考えられます。
周囲の反応をうかがうことで愛情を確認する「試し行動」も、子どもも成長過程でみられることが多くあります。発達障害の子どもの「試し行動」。問題行動への対応は?をあわせてお読みください。

家庭での「遊び食べへの指導」テクニック
長期的な遊び食べは「食事のマナー」を教えていくことが対処法のひとつです。ASDがあると常識を習得しづらい?上手な教え方は|中高生向けでもお伝えをしたとおり、特性があるお子さまは自然とルールを身につけることが難しいケースがあります。
「食べ物は落としてはいけない。落としたごはんは食べられないから」「食事中にほかのことをしてはいけない。食べ物に集中ができなくなって消化が悪くなるから」など年齢に応じてルールを教えていくようにしましょう。
感情的にならず冷静に、やってはいけないこととその理由を明確に伝えるようにしましょう。
注意をしてもおさまらない場合には、思い切って食事を終わらせることも対処法のひとつです。「○○をしたらごはんは終わり」とルールを子どもにとって分かりやすく伝えるためです。

ADHD特性によって、食事中に立ち歩いたりテレビに気を取られたりする場合には、注意がそれるものをお子さまの視界に入れないようにしましょう。食事に集中できる環境を作ることが大切です。
また、ごはんの時間を事前に伝える(「〇時~〇時は晩御飯の時間だよ」等)ことで見通しを持たせることも有効です。「〇時まではごはんだけど、そのあとは○○ができる」と思わせることで、「食べること」に注意を向けやすくなります。
食事をすること自体が苦手だったり、興味がなかったりするお子さまの場合には、「食事を楽しい時間」であると思わせるための工夫を取り入れることもおすすめです。
お子さまが食事をする様子を見守りながら、「おいしそうだね」「きれいに食べられたね」と明るい表情で声がけをするなど、楽しい雰囲気を作ることが大切です。
良くない行動をしたときも、強く叱ったり、イライラした表情を出したりせずに、冷静に対応しましょう。「怒られた」という記憶を持たせないためです。
ごはんを食べ終わったら好きなことができる(アニメを見る、デザートを食べる等)というご褒美を提示するのもよいでしょう。

一人で悩まず、相談することも大切
忙しい日々の中で、お子さまの「遊び食べ」にどうしてもイライラしてしまう…と悩む保護者の方は少なくありません。
成長過程で必要なこと、特性だからしかたないことと分かりつつも、ストレスを抱えてしまうこともあると思います。強く叱りつけてしまいたくなる気持ちをぐっとこらえて、子どもが「食事嫌い」にならないようにサポートをすることは大切なことでありつつも、保護者の方にとって非常に労力がかかることです。
ひとりで悩まず、専門機関に相談をしてみることをぜひ検討してみてください。
発達障害は目に見えず分かりづらい障害だと言われており、さらに一人ひとり特性が異なることから、家庭内だけでは特性へのアプローチがうまくいかないケースがあります。
児童発達支援「ハッピーテラスキッズ」放課後等デイサービス「ハッピーテラス」では、発達に課題のあるお子さまへの療育だけではなく、その保護者の方へのサポートもおこなっています。
お子さまの特性への理解を深めたい、家庭での療育の方法を知りたい、園・学校との連携について教えてほしいなどのご希望のある方は、ぜひお近くの教室にご相談ください。



 0120-115-423
0120-115-423